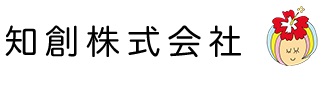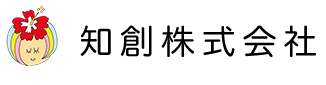昨日行った療育アドバイザー松本先生によるアナログゲーム療育の模様をお伝えします。
今回も発達レベルに合わせて2つのグループを編成し、セッションを行いました。
実は、このグループ分けはとても重要で、毎回セッション後のフィードバック(反省会)で、各お子さんのゲームへの参加度合いやアセスメント内容を考慮し、決定しています。
アナログゲーム療育は基本的にグループ(集団)セッションではありますが、松本先生はじめスタッフの皆さんで、それぞれのお子さんを個別に考察しています。
ではグループ①のスティッキィの様子から。
 これは、色の理解力を促す狙いがあります。
これは、色の理解力を促す狙いがあります。
他にグループ①ではパカパカお馬という比較的簡単なすごろくゲームを行いました。すごろくゲームは全般に数の概念理解に役立ちます。
続いて、グループ②の様子です。
 どうですか?この密集度!(笑)
どうですか?この密集度!(笑)
前にも書きましたが、松本先生やスタッフからの指示で行う療育ではなく、お子さん達同士で自発的に楽しみながら行えることがアナログゲーム療育の最大のメリットです。
 これは「なんじゃもんじゃ」で、頭と手足だけの謎生物“ナンジャモンジャ”族12種類のカードが中央の場に次々とめくられるたびに、思い付きの名前を与え、後で同じものが出たら、その名前をいち早く叫ぶことで場のカードを獲得し、集めた枚数を競うゲームです。
これは「なんじゃもんじゃ」で、頭と手足だけの謎生物“ナンジャモンジャ”族12種類のカードが中央の場に次々とめくられるたびに、思い付きの名前を与え、後で同じものが出たら、その名前をいち早く叫ぶことで場のカードを獲得し、集めた枚数を競うゲームです。
かなり白熱していたようです(^^♪
 今回初登場の「アルミかん」というゲームです。松本先生の大きなキャリーバック(通称:四次元ポケット)には、一体いくつの新作ゲームが入っているのでしょうか(笑)
今回初登場の「アルミかん」というゲームです。松本先生の大きなキャリーバック(通称:四次元ポケット)には、一体いくつの新作ゲームが入っているのでしょうか(笑)
このグループの中には、新一年生も入っています。グループ分けの際、実年齢や学年も考慮しますが、当然、低学年でも発達レベルの高いお子さんは、このようにお兄ちゃん、お姉ちゃん達に交じってゲームに参加しています。
実はこの1年生の○○さん。お兄ちゃん達にも負けず劣らず、すばらしい能力を発揮しました!
話は変わりまして社内の話になりますが、4月より松本先生には、アナログゲーム療育の講師としてだけでなく、スタッフへの研修の実施、設備の環境整備(構造化)や個別支援計画・アセスメントシートの見直しなどオルオルハウス全体のアドバイザーとして務めていただいています。
来週の26日火曜日に、第一回目の管理者ミーティング(個別支援計画や設備環境設定)とスタッフへの内部研修を行っていただきます。
松本先生のお力添えを頂きながら、さらなる質の向上を目指していきます<m(__)m>
オルオルハウスかすみ